医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1634件

糖尿病足病変発症のリスクからフットケアとセルフケア支援が必要な患者さんに関する看護計画
NEW
糖尿病足病変発症のリスクからフットケアとセルフケア支援が必要な患者さんに関する看護計画 糖尿病はインスリン分泌低下あるいはインスリン抵抗性による慢性的な血糖値の上昇とそれに伴う異常が生じる疾患です。その合併症の一つとして動脈硬化が起こり足病変を生じるリスクが高くなるため、
2026/2/6

痰の分泌が多い気管切開をしている患者さんに関する看護計画
痰の分泌が多い気管切開をしている患者さんに関する看護計画 気管切開の患者さんは、救急や集中治療などの急性期から、地域在宅や療養施設などの慢性期まで幅広くみられます。自力で痰を出せない状態や上気道が閉塞する状態、長期に人工呼吸器が必要な状態などの場合に選択されます。そこで、
2026/2/2

第4回 高齢者や施設での糖尿病患者さんへのフットケアQ&A【PR】
左から末丸大悟 医師、松本夏希 医師、石川恵 看護師 糖尿病患者さんに起こる足病変について前橋日赤糖友会で療養指導に携わる医師および看護師に、ナース専科の読者のみなさんから寄せられた質問に回答していただきました。 Q1 目が悪い患者さんのセルフモニタリング、下肢の
2026/1/23

第3回 糖尿病看護に大事なこと|足病変の早期発見、早期介入、患者さんへのケアQ&A【PR】
左から末丸大悟 医師、松本夏希 医師、石川恵 看護師 糖尿病患者さんに起こる足病変について前橋日赤糖友会で療養指導に携わる医師および看護師に、ナース専科の読者のみなさんから寄せられた質問に回答していただきました。 糖尿病看護に大事なこと 糖尿病患者さんの看護に
2026/1/21

アセスメントに生かす体性感覚とは?|日々の看護ケアに活かす末梢神経を看護の視点でおさらい!
今回の問題看護師国家試験第112回-午前-必修10 体性感覚はどれか。 1.視覚 2.触覚 3.聴覚 4.平衡覚 回答 2 問題の解説 体性感覚とは、皮膚や筋肉や関節などのさまざまな部位からの情報を受け取り、末梢
2026/1/20

第2回 糖尿病足病変を発症させないためのフットケア【PR】
左から末丸大悟 医師、松本夏希 医師、石川恵 看護師 糖尿病患者さんに起こる足病変について前橋日赤糖友会で療養指導に携わる医師および看護師にご解説いただきました。 糖尿病足病変のハイリスク要因 2008年に診療報酬が改定され、医師や看護師、患者さんの要件等を満
2026/1/16

第1回 糖尿病足病変とは【PR】
左から末丸大悟 医師、松本夏希 医師、石川恵 看護師 糖尿病患者さんに起こる足病変について前橋日赤糖友会で療養指導に携わる医師および看護師にご解説いただきました。 糖尿病の合併症とは 糖尿病の罹病期間が長くなると、徐々に慢性合併症が起きてきます。それらは、①細
2026/1/14
第19回 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)学術集会【参加登録のお願い】
一般社団法人 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)の第 19 回学術集会を開催いたします。 (当番会長:齊藤 雅也<社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院>) リーダーズは、静脈栄養と経腸栄養を駆使した栄養管理について徹底的に議論することを目的としています。 ただいま参
2026/1/13

循環動態が不安定な患者さんの褥瘡予防について知りたい!
Q.循環動態が不安定で、体位交換が困難な患者さんがいます。グローブを使ってこまめに除圧したり、エアマットレスを使ったりしても褥瘡ができてしまいます。循環動態が不安定な患者さんの褥瘡予防について教えてください。 A.褥瘡予防に特別なことはなく、基本が重要です。体位変換が困
2025/12/10
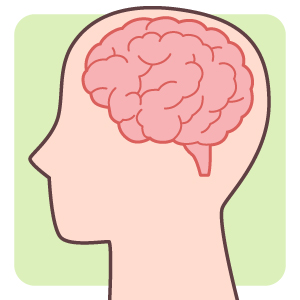
慢性硬膜下血腫の術後のドレナージ管理のポイントが知りたい!
Q.慢性硬膜下血腫における術後のドレナージ管理のポイントについて教えてください。 A.指示された安静度やドレーンの高さを維持するとともに、ドレナージ回路、排液の量・色調などの確認を行い、適切にドレナージできているか確認します。 慢性硬膜下血腫とは 脳
2025/12/8

病棟でも外来でも扱う輸血製剤、それぞれの特徴とは?
今回の問題看護師国家試験第112回-午前-一般41 輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。 1.血小板成分製剤 ── 2〜6℃ 2.赤血球成分製剤 ── 2〜6℃ 3.血漿成分製剤 ── 20〜24℃ 4.全血製剤 ── 20〜24℃
2025/12/4
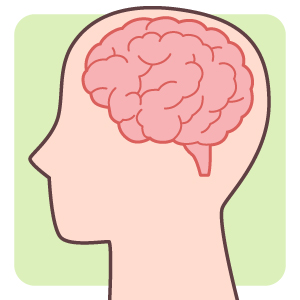
脳室ドレナージで血性髄液の排出が持続。すぐにクランプしたほうがよい?
Q.脳室ドレナージ中の急性期の患者さんで血性髄液の排出が持続した場合、すぐにクランプしたほうがよいですか? 適切な対処の仕方を教えてください。 A.すぐにクランプすることは原則として避けるようにします。原因により対処方法が変わるため、まずは、意識レベルや神経症状、ドレ
2025/12/2

まんがでわかる緩和ケアSTORY― 第2話 未来、がん患者さんの痛みを学ぶ【PR】
看護師の未来が緩和ケアを学んでいくお話の【第 2 話】です。ご覧ください!
2025/12/2
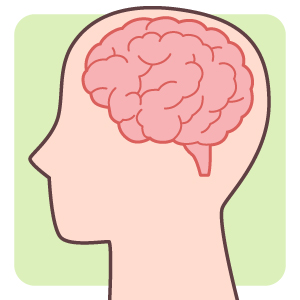
スパイナルドレーン留置中の患者さんに清拭を行うときの注意点が知りたい!
Q.スパイナルドレーンを留置している患者さんの清拭をしたのですが、何に気を付ければよいかわからず、非常に怖いと感じました。スパイナルドレーンを留置している患者さんに清拭を行う際の注意点を教えてください。 A.清拭時はドレーンの事故抜去、オーバードレナージ、感染などに注
2025/11/29
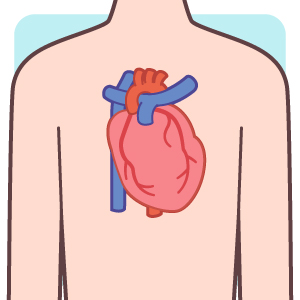
血管内治療(EVT)後の安静時間はどれくらい?
Q.血管内治療後は安静指示が出ますが、座位や歩行ができるようになるまで、安静時間はどれくらい必要になりますか? A.血管内治療後の安静時間について、明確に定められた一律の基準はありません。そのため、実際の臨床現場では、各施設が独自にプロトコールを設け、医師や看護師を含む医
2025/11/28


