医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1635件

第8回 子どもに現れる反応(後編)
病気に対する親の不安が、子どもの体に現れる場合も 前編で述べてきたように、親ががんになった場合、感情面、行動面での変化が子どもには多く見られます。特に、親が強い不安をもつ場合は、子どもに与える影響も大きく、子どもも強い不安を抱くようになるといわれています。泣いたり、怒る
2011/9/6

第7回 子どもに現れる反応(前編)
子どもは、親の病気やそれに伴う生活の変化に巻き込まれたとき、子どもなりに「これまでと違うこと」を察知します。子どもに過大な不安を抱かせないためには、親の病気を伝えていくことが必要となるでしょう。それと同時に、子どもが親の病気についてどう感じているか、子どもの心の変化を把握
2011/8/30

【発汗異常の看護】発汗異常の原因とアセスメント・ケアのポイント
発汗は体温調整の生理現象の一つです。 しかし、いつになく発汗過多がみられたら、そこには何か異常が起こっている恐れがあります。 まずは、これを知っておこう! ■熱の産生と放出のバランスが取れているかを考える 発汗は基本的に生理現象です。私たちの体内では
2011/8/30

第6回 パパやママの病気を子どもに知らせる方法(後編)
がんと診断された患者さんが子どもにその事実を伝えるとき、どのような情報をどのように伝えればよいのでしょうか。子どもに病気であることを話すときのポイントを紹介します。 がんを伝えるときポイントとなる3つのC 親にがんと告げられたとき、子どもが混乱する大きな原因の一つ
2011/8/23

第5回 パパやママの病気を 子どもに知らせる方法(前編)
がんなどの死に至る深刻な病気を発症した場合、その事実を子どもに伝えるべきか、あるいは伝えないでいるべきかは、重大な問題の一つです。迷いをもつ患者さんが、医師や看護師などの医療者にアドバイスを求めることも少なくありません。子どもに親の病気を伝えるときには、何に配慮し、どのよ
2011/8/16

【口渇の看護】口渇の原因とメカニズム(脱水・ドライマウス)、アセスメント
口が渇く原因は、脱水症によるものと口の中だけが渇くものに分けられます。 脱水症に起因している場合は、緊急対応が必要なケースもあります。 口渇のメカニズムやアセスメントの仕方を知って、 どちらに起因しているのかを鑑別し、適切な看護につなげましょう。 まずは、これを
2011/8/15
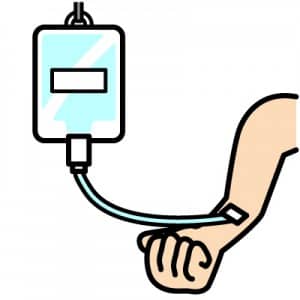
第24回 栄養管理の重要性
『看護師のための輸液管理』というテーマで24回、連載させていただきました。その最終回のタイトルは『栄養管理の重要性』としました。輸液管理は、ある意味、栄養管理の一環として行う、ということでもありますから。 輸液管理とリスクマネジメント ナースにとって、日常業務の中
2011/8/10

第4回 年齢によって「死」の捉え方は どう違うか(後編)
前編に続き、年齢による親の病気や死の捉え方の違いについて考えていきます。特にかかわりが難しいという声を聞く思春期の子どもたちについて、彼らにはどのように接していくのが望ましいのでしょうか。 思春期の子どもにはかかわりにくい? 子どもというと、どうしても小さな子ども
2011/8/9

第3回 年齢によって「死」の捉え方は どう違うか(前編)
親をはじめ、子どもにとって大切な人が亡くなる場合、そのことを事前に知らせることは、子どもの発達の面からも大切です。死を伝えることで、決して悲しみが軽くなるわけではありませんが、残された時間を意識しながら一緒に過ごし、子どもなりのお別れができるからです。「子ども」と一言でい
2011/8/2

第2回 亡くなる患者さんの子どもとのかかわりに迷う理由(後編)
死を前にした患者さんの子どもには、どのようにかかわり、親の死を伝えればよいのでしょうか。患者さんや子どもをとりまく状況面から考えた、医療者側によるアプローチの可能性について、具体的に考えていきます。 なぜ、子どもへのケアが大切なのか? 子どもも大人と同様に、大切な
2011/7/26

第1回 亡くなる患者さんの子どもとのかかわりに迷う理由(前編)
死を前にした患者さんの家族に、成人前の子どもがいるケースは少なくありません。そのような子どもに対して、「どう声をかけていいのか、迷ってしまう」「何をすればいいのか、わからない」などと悩んだり、戸惑ったことがあるのではないでしょうか。 第1回は、現場でそのような戸惑いの生
2011/7/14
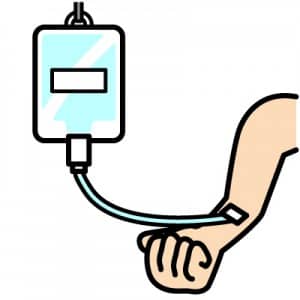
第22回 CRBSI予防対策は当然のこととして実施されていなければならない!
CRBSIとは、Catheter-related bloodstream infectionの略語で、血管内留置カテーテル関連血流感染症と日本語では表現されています。かつてはCRS:catheter related sepsis、カテーテル敗血症という簡単な用語が使われていた
2011/5/16
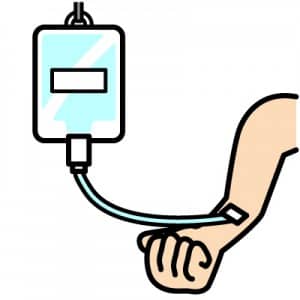
第21回 上腕ポートについて
ポート(図1)。既に説明しましたね。使用方法、合併症、利点や欠点、などについてはもう理解していただいていると思います。 さて、ポートを使う目的は何だったでしょうか?具体的なことは別にして、とにかく、ポートを使わない期間には投与ラインから解放され、さらにポート自体が皮下に埋
2011/3/22

日本フットケア学会レポート
2月9、10日に、パシフィコ横浜にて「第11回日本フットケア学会/第5回日本下肢救済・足病学会 合同学術集会(会長:埼玉医科大学・市岡滋さん)」が開催されました。フットケアに関するさまざまな内容の講演が行われ、今回はその中から教育講演「糖尿病治療の最前線ー足病変予防・治療
2011/2/20

【皮膚異常の看護】皮疹(ひしん)の種類と緊急性の判断
皮膚に出た異常が、実は重篤な疾患や緊急を要する疾患のサインであるケースもあります。 目に見える症状の下に隠れた部分を見逃さないようにしましょう。 皮疹の種類と特徴 まずは、これを考えよう! ■皮膚の異常を見落とさないためにも、どんなものがあるのかを知っておこ
2011/1/12


