医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1629件

【排泄・スキンケア】嵌入便のケアなど5つのワザ
ワザ1 心理的影響が強い頻尿なら、安心感を与える! 頻尿の原因が失禁への不安である場合、その不安を軽減することが第一です。トイレまでの距離が心配なのであれば、ポータブルトイレを使ったり、トイレまで近い病室に変更するなど、移動時間をできるだけ短くすることで不安を軽減し
2014/7/27

下痢のとき、 まずどうする?下痢しやすいおもな薬剤
A 原因によって対処が異なるので、原因を見極めます 下痢の主な原因には、以下4つがあります。 ①浸透圧性下痢:未消化の大量の食物等により腸壁から大量の水分が分泌する ②滲出性下痢:細菌やウイルスにより腸粘膜が炎症を起こす ③分泌性下痢:難治性潰瘍な
2014/7/26

【頻回な夜間のトイレ、便秘の看護など】排泄ケアのアセスメントの3つのポイント
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。 排泄 1 頻回な夜間のトイレ──頻尿なのか、不眠なのかを見極める 患者さんが頻尿の場合、排尿状況を確認し、その原因を考えます。排尿状況の確
2014/7/25

輸液療法とは? 輸液療法の目的と基本
どんなケースにも共通する輸液管理の基本的な考え方について整理しておきましょう。 【輸液のまとめ記事】 * 輸液の看護|輸液とは?種類、管理、ケア 輸液療法の目的 ●「火元対策」としての原疾患の治療 ●「火の粉対策」としての合併症に対す
2014/7/24

加齢が排泄・スキンケアにもたらす「6つの悪影響」
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。今回は、「加齢がもたらす悪影響」です。 [排泄にかかわる機能への悪影響] 影響1 膀胱機能・尿道機能が低下する →残尿感/頻尿/失禁
2014/7/24

【問題1】500mlを60ml/h 小児用ルートで投与する時、30秒間の滴下数は?
問題 小児用ルートを使用して、○○輸液500mlを60ml/hで投与する指示を受けました。 30秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです 解答 30滴 解説 小児用ルートは1ml
2014/7/24

高齢者の睡眠障害|アセスメント・看護ケア
睡眠障害は、加齢に伴う身体機能の低下だけでなく、環境適応能力の低下、治療薬の影響、せん妄などさまざまな要因によって引き起こされます。 ▼関連記事 認知症・認知機能障害の看護ケア|原因、症状、アセスメントのポイント 睡眠障害かどうかをアセスメン
2014/7/23

5%ブドウ糖液と生理食塩液(生食)の役割って?
治療の一環として日常的に実施される輸液。でも、なぜその輸液製剤が使われ、いつまで継続するのかなど、把握できていない看護師も意外と多いようです。まずは、輸液の考え方、輸液製剤の基本から解説します。 輸液製剤、何が違う? どう使う? 輸液製剤には、大きく水
2014/7/22

第3回 患者さんへの薬の説明ポイント
処方薬の多い現在、正しい服用のためには薬剤師、そして患者さんの最も近くにいる看護師の支援が必要になってきます。内服薬を中心に服薬支援のポイントを紹介します。 患者さん自身が必要性を認識できるようなサポートを 治療効果を上げるためには、正しく服薬が行われ
2014/7/22

【看護倫理・事例】第4回 苦痛が目標を阻害するケース
日々の看護のなかに意外に多く潜んでいる倫理的問題。それらの解決のためには、倫理的問題に気づくセンスが欠かせません。 今回は、患者さんの意思決定にまつわるケースを通して問題を掘り起こしてみましょう。 今回のケース 起き上がりたい、でもコルセットはし
2014/7/22
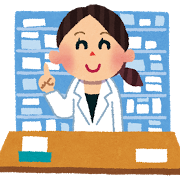
半消化態栄養剤 「エネーボTM配合経腸用液」が発売
アボット ジャパン株式会社は、2014年5月30日に半消化態栄養剤「エネーボTM配合経腸用液」を発売しました。本剤は、医療用医薬品の半消化態栄養剤として15年ぶりの新製品です。 最大の特徴は、医薬品経腸栄養剤として国内初となる栄養成分を15種類(後述)配合しているこ
2014/7/22
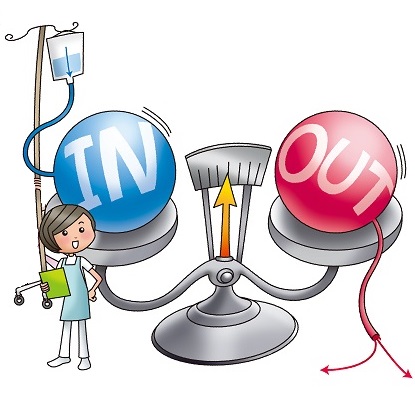
IN/OUTバランスがわかると【血液ガス】がわかる!
IN/OUTバランスに関係の深い疾患の診断や治療について、輸液の側面からみていきましょう。 疾患と輸液の関係を具体的にみることによって、IN/OUTバランスについてさらに理解を深めましょう。 アシドーシス・アルカローシス 判断の手順 手順1 pH
2014/7/21
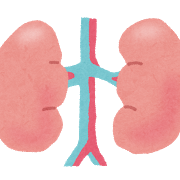
IN/OUTバランスがわかると【腎不全】がわかる!
IN/OUTバランスに関係の深い疾患の診断や治療について、輸液の側面からみていきましょう。 疾患と輸液の関係を具体的にみることによって、IN/OUTバランスについてさらに理解を深めましょう。 腎不全の病態と輸液 腎不全には、急性腎不全と慢性腎不全
2014/7/20

中枢神経・運動系アセスメント―意識レベルの評価と脳幹の障害の評価
アセスメントは、患者さんとの会話やケアを通じて全身の状態に目を向け、五感をフルに活用することが大切です。ここでは系統別にフィジカルアセスメントのテクニックをまとめました。普段行っているアセスメントの流れと手技を再確認してみましょう。 中枢神経・運動系のフィジ
2014/7/19
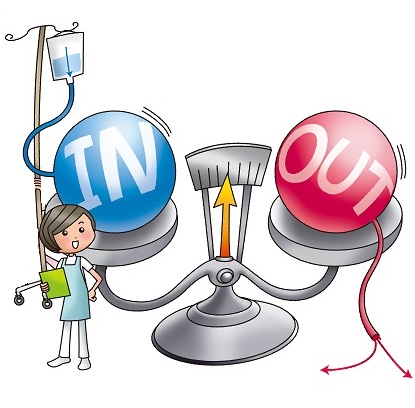
生食とブドウ糖液は体内をどう移動する?
生食とブドウ糖液は体内をどう移動する? 輸液を1L入れても、循環血液量が1L増えるわけではありません。細胞内液と細胞外液の分布や組成の違い、特性などを知っておけば、どこに何のために輸液をするのか、輸液の目的を理解したうえで看護にあたることができます。
2014/7/19


