医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1632件

最終回 ケースで考える率直な会話のための言葉かけ
がん患者さんへの言葉かけトレーニングもいよいよ仕上げです。最終回は、これまでのレクチャーを踏まえて、2つのケースについて考えてみましょう。あなたは患者さんにどんな言葉をかけますか? Case1 転移を告げられた直後の患者さん。訪室したあなたが言葉をかけるとしたら?
2012/5/23
【急性期の褥瘡】経過観察とケア
急性期と慢性期の褥瘡では、創を見るための視点がことなります。まずは、急性期の褥瘡から、アセスメントのポイントを解説していきます。 ▼褥瘡ケアについてまとめて読むならコチラ 褥瘡とは?褥瘡の看護ケア|原因と分類、評価・予防・治療など 急性期の褥瘡の経過とケア
2012/5/21

第7回 【がん看護】患者さんとの会話のポイント
がん患者さんとの会話では、時に死や無念さといった深刻な話題になることも少なくありません。そんなときに、どう答えていいかわからないままに、通りいっぺんの返答をしては、患者さんとの言葉のキャッチボールは生まれません。 ここでは、看護師が自分の言葉で率直 な会話をするための基
2012/5/10
見やすく抜けにくい留置針の「ルート固定方法」
点滴時の留置針の固定は、刺入部が観察しやすく、抜けにくくしておきたいものです。今回は、留置針の固定方法について解説します。 Q. 点滴時の留置針の刺入部が、見やすく抜けにくい固定方法を教えてください。 A. 刺入部が観察しやすいフィルムドレッシング材で固定し、ライ
2012/5/7

第6回 緩和ケアへの移行時に抱えるストレス
心身状態が悪化し、生活に支障が出るなか、残された時間をどう過ごしたいかという思いを捉えることが大切です。 緩和ケアへの移行時に抱えるストレス 抗がん治療の中止は、もはやがん疾患に対する手立てがないということを意味する場合が少なくありません。その場合、患者さんにとっては
2012/5/3
滴下速度の変化にどう対応する?
滴下速度をきちんと計算しても、いつの間にか変わってしまっていたという経験がある人は多いのではないでしょうか。この滴下速度の変化に関する疑問に答えます。 Q. 滴下速度をきちんと計算しても、滴下数が変わってしまうことがあります。滴下速度の変化を防ぐ方法はあるのでしょう
2012/4/30

第5回 【がん】再発・転移時に抱えるストレス
再発や転移が明らかになったとき、治癒が望めなくなった衝撃とともに、身体症状も現れ始めます。治癒についての不安を解消し、信頼関係の再構築が必要です。 再発・転移時に抱えるストレス がん患者さんにとって、最も大きな苦悩の時期の一つが、再発・転移のときです。 初発のと
2012/4/26
チューブ・カテーテルのルート交換頻度ってどれくらい?
末梢静脈ルート、中心静脈カテーテル、胃管チューブなど各種ルートはどれくらいの頻度で交換するのがよいのでしょうか。感染管理の面からも、交換のタイミングは大切になります。根拠とともに、それぞれのルートの交換のタイミングを知っておきましょう。 Q. 末梢静脈ルート、中心静
2012/4/23
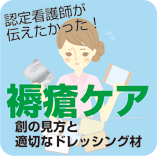
この褥瘡に最適なドレッシング材を選ぶ!
この連載では、創の見方と適切なドレッシング材の選び方について解説していきます。 まずは、ドレッシング材について基本のポイントを押さえておきましょう。 褥瘡のまとめ記事 * 褥瘡とは?褥瘡の看護ケア|原因と分類、評価・予防・治療など ドレッシング材の目的 日本
2012/4/23

第4回 【がん】治療中~経過観察期のストレス
体力が回復してからも、再発・転移の不安が続く時期。不安を抱え込まないための言葉かけや情報提供を行っていくことが大切です。 治療中~経過観察期 患者さんの身体と心 入院しての手術や化学療法などの初期治療から、退院後の通院治療へと、患者さんの生活は大きく変わっていき
2012/4/19

第3回 【がん】告知から治療方針の選択時に抱えるストレス
告知から治療方針が決定するまでは、受け入れがたい現実に対して、否認、怒り、楽観などの反応が現れる時期です。がん患者さんの抱える問題は、個々の社会背景などによってさまざまですが、いつでも支援できることを伝えておきたいものです。 告知~治療方針の選択時に抱えるストレス
2012/4/13
気管吸引 実施の見極めポイント
気管吸引は2時間ごとなど、時間を決めて定期的に行うものではなく、実施するかどうかはアセスメントを行って決定します。 では、アセスメントの際はどこを見て判断するとよいのでしょうか。 今回は、気管吸引が必要かどうかを見極めるためのアセスメントのポイントを解説します。
2012/4/9

第2回 ベッドサイドで看護師とかわす会話
がん患者さんの心のケアとして大切な役割を果たすのが、「ベッドサイドで看護師とかわす会話」です。では、具体的にどのように会話を進めていけばいいのか、ポイントを紹介します。 言葉のキャッチボールができるように ──日々の心のケアとして、病棟看護師は何をすればよいですか
2012/4/6
人工呼吸器装着時の吸引の手技・手順とは?
人工呼吸器装着患者さんの吸引を行う際、いつも行っていることなのでなんとなく行ってしまっていませんか。今回は、吸引の正しい手技と手順、ポイントをおさらいしていきましょう。 Q. 人工呼吸器(気管挿管)を装着している患者さんの吸引の正しい手技とポイントを教えてください。
2012/4/2

第1回 がん看護さんの相談で多いものは?
がん患者さんが必要とする心のケアとは、どのようなものなのでしょうか。がん看護相談などの実践からは、「情報を求めている」という最近の傾向が明らかになっています。 そしてもう一つ、心のケアとして大切な役割を果たすのが、「ベッドサイドで看護師とかわす会話」です。精神看護専門看
2012/3/29


